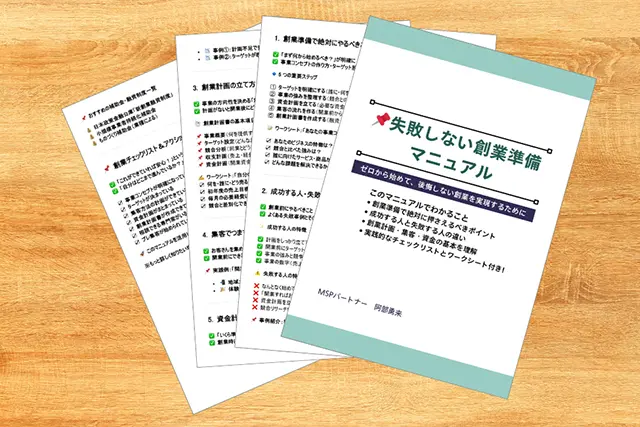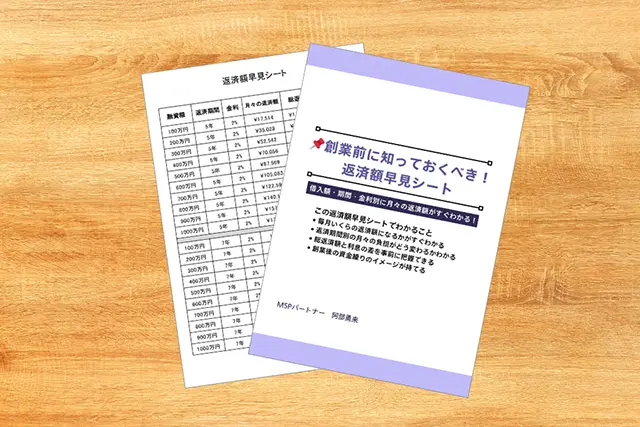“創業計画書の書き方を調べてる人ほどハマる落とし穴”とは?
創業準備・マインドセット
2025年4月24日
〜創業計画書でやってはいけない3つのこと〜
こんにちは。
山形県庄内エリア(酒田市・鶴岡市)を中心に、
創業・売上アップ・集客支援を行っている
**MSPパートナーの阿部勇来(あべゆうき)**です。
地域で挑戦する事業者さんが、
理想のお客さんが自然と集まる仕組みをつくれるよう、
“実践”にこだわってサポートしています。
今日もブログをお読みいただき
ありがとうございます。
それでは、本題です。
「創業計画書 書き方」で検索していませんか?
創業融資を受けるために「創業計画書を作らなきゃ」と思い、
ネットで“書き方”を調べてテンプレ通りに埋めていく——。
実はこの時点で、多くの人が同じ“落とし穴”にはまっています。
“通る計画書”と“成果につながる計画書”は違う。
今回は、個人事業主の方がやってしまいがちな
「創業計画書でやってはいけない3つのこと」をお伝えします。
①「とにかくそれっぽく書けばいい」になっている
ネットで出てくる例文やテンプレをそのまま写して、
中身のないキレイな文章で埋めてしまう。
これ、実は何の意味もありません。
- 「地域貢献したい」
- 「お客さまの笑顔のために」
- 「安心・安全をお届けします」
どれも悪くはないけれど、“あなたならでは”が伝わらないと評価されません。
回避法:
→ あなた自身の背景や経験からくる「想い」を言葉にしましょう。
テンプレより、“自分の言葉”が何よりも伝わります。
② 数字に根拠がないまま“それっぽく”書いている
- 月売上 30万円
- 客単価 3,000円
- 経費 合計 15万円
一見まとまって見える数字でも、「どうしてその数字なの?」と聞かれたときに答えられないのはNG。
回避法:
→ 例えば
「1日3人×客単価3,000円×月25日営業=月売上225,000円」
というように、計算式が成り立つように設計しましょう。
特に個人事業主の場合、自分の稼働時間・キャパシティから逆算するのがポイントです。
③ 書類を“提出物”としか考えていない
融資が通ったら創業計画書は見返さない。
そんな人は、創業後に迷子になります。
計画書は「通す」ためのものではなく「使う」ためのもの。
回避法:
→ 創業後に見直せるよう、行動スケジュールや集客導線まで具体化しておく。
たとえば:
- 開業1ヶ月前にSNSを開設
- 初月は体験キャンペーンで新規を10人集める
- 2ヶ月目からLINEでの予約導線を整える
こうした「やること」まで計画に含めれば、開業後の“迷い”が激減します。
まとめ|創業計画書は“行動の設計図”
創業計画書は、“審査に通すための書類”というよりも、
自分のビジネスを形にしていくための“地図”です。
- 他人の言葉を借りず、自分の言葉で書く
- 数字に根拠を持たせる
- 開業後の行動計画まで落とし込む
この3つを押さえておけば、融資にも通りやすく、その後のビジネスもスムーズにスタートできます。
\無料で相談できます!/
「書き方は調べたけど、本当にこれでいいのか不安…」という方は、
LINE登録からお気軽にご相談ください。
“テンプレじゃない、使える計画書”を一緒に整えていきましょう!