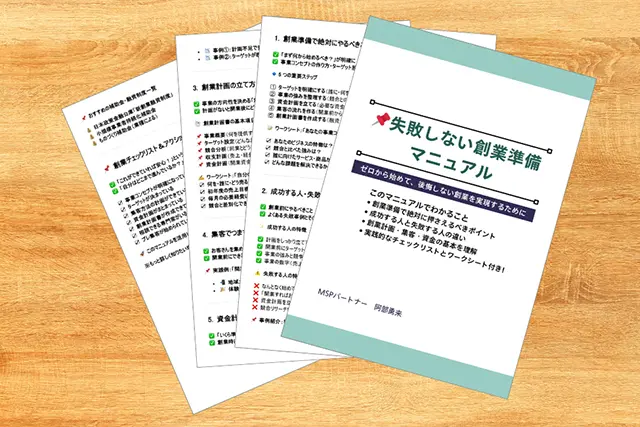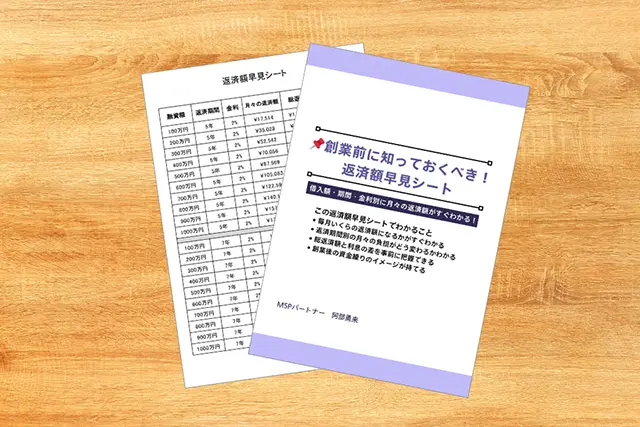「創業計画書って、何を書けばいいの?」と悩む方へ
創業準備・マインドセット
2025年4月21日
こんにちは。
山形県庄内エリア(酒田市・鶴岡市)を中心に、
創業・売上アップ・集客支援を行っている
**MSPパートナーの阿部勇来(あべゆうき)**です。
地域で挑戦する事業者さんが、
理想のお客さんが自然と集まる仕組みをつくれるよう、
“実践”にこだわってサポートしています。
今日もブログをお読みいただき
ありがとうございます。
それでは、本題です。
「創業計画書って、正直よくわからない…」
創業を考えはじめたとき、多くの人が最初にぶつかる壁がこれです。
- 「テンプレートを見ても、ピンとこない」
- 「どこから書き始めればいいのか迷う」
- 「正解があるようで、ないようで…不安になる」
でも大丈夫です。最初から完璧に書ける人なんていません。
実は、“書き方”よりも大事なのは、“どう向き合うか”という考え方なんです。
創業計画書は「提出用の書類」ではなく「未来の設計図」
多くの方は、創業計画書を
「融資のために必要な書類」だと考えています。
もちろんそれも大事な目的ですが、
本当に価値があるのは、**“自分のビジネスの軸が見えてくること”**です。
- 誰のためのビジネスか
- どんな価値を届けたいのか
- どうやってお客さんに知ってもらうのか
- どれくらいの売上・経費・利益が必要なのか
このように、創業に向けての整理と覚悟を固めるための設計図なんです。
「とりあえず埋める」では意味がない理由
創業支援の現場では、
「数字はとりあえずで…」
「ターゲットもなんとなく決めました」
という声をよく聞きます。
でも、それでは机上の空論になってしまい、創業後にブレやすくなります。
- 想定より集客に時間がかかる
- 思っていたより経費が高くて苦しい
- 誰をターゲットにしていたか自分でも忘れてしまう
こうなる前に、最初の計画段階で“本気で考えておく”ことが、失敗を減らす最大の近道です。
書き方より先に“考えるべき3つの視点”
では実際に創業計画書に向き合うとき、
どんな視点を持つといいのでしょうか?
以下の3つを意識すると、グッと書きやすくなります。
①「誰に届けたいか?」を明確にする
→ ターゲットを具体的に描けると、発信・価格・サービス内容が決まりやすくなります。
②「どんな変化を与えるか?」を考える
→ 商品・サービスの“価値”は、スペックではなくビフォーアフターで伝えると整理しやすいです。
③「どうやって届けるか?」を現実的に想像する
→ SNS・LINE・チラシ・紹介など、現場ベースで導線を設計することがカギです。
まとめ|創業計画書は、“未来と向き合う時間”
「何を書けばいいの?」と迷うのは当たり前です。
でもそれは、まだ“自分のビジネスとちゃんと向き合っていない”だけかもしれません。
創業計画書は、融資のためではなく、
あなた自身が安心してスタートするための道しるべです。
「書くこと」が目的ではなく、
「考えること」こそが大事。
その考えを一緒に整理したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
\無料で相談できます!/
創業計画書に向き合いたいけど、どこから始めていいかわからない…
そんな方は、LINE登録からお気軽にご連絡ください。
あなたに合った形で、一緒に整理していきましょう!