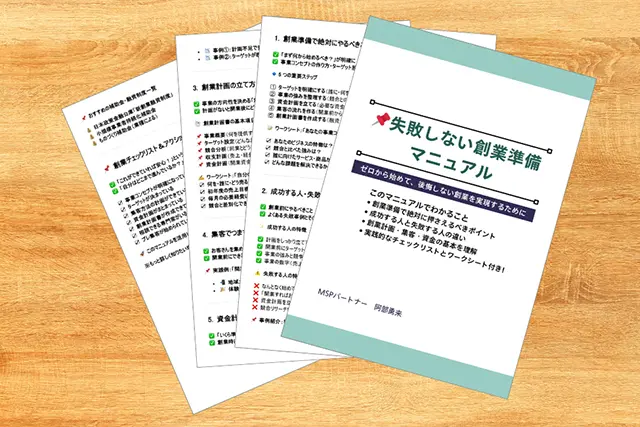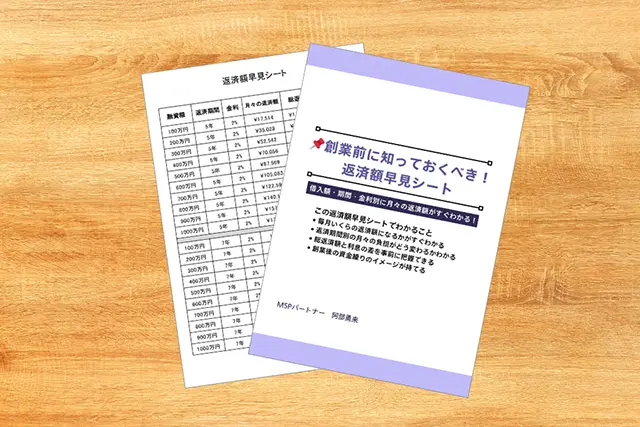「とりあえず埋めた創業計画書」は危険!
創業準備・マインドセット
2025年4月25日
〜創業計画書でよくある失敗とその回避法〜
こんにちは。
山形県庄内エリア(酒田市・鶴岡市)を中心に、
創業・売上アップ・集客支援を行っている
**MSPパートナーの阿部勇来(あべゆうき)**です。
地域で挑戦する事業者さんが、
理想のお客さんが自然と集まる仕組みをつくれるよう、
“実践”にこだわってサポートしています。
今日もブログをお読みいただき
ありがとうございます。
それでは、本題です。
「とりあえず埋めて出した」では意味がない
日本政策金融公庫などに提出する「創業計画書」。
- フォーマットがある
- 記入欄が多い
- 一度で通るか不安
そんなプレッシャーから、
「とりあえず全部埋めればOKだろう」と、なんとなくで記入してしまう方も多いです。
でも実は、これが後々の“創業トラブル”の原因になることも…。
よくある創業計画書の失敗例とその回避法
① 内容が抽象的で、誰のための事業かわからない
例:「地域に貢献するカフェを開業します」
よく見かけるフレーズですが、これだけでは事業のイメージが伝わりません。
回避法:
- 誰に(例:子育てママ、テレワークの方)
- どんな価値を(例:リラックスと集中できる空間)
- どのように届けるか(例:キッズスペース+Wi-Fi完備)
を具体的に記載しましょう。
“言い換えればチラシにも使えるくらいの明確さ”が理想です。
② 数字に根拠がなく、現実性に欠ける
例:「売上目標 月30万円(根拠なし)」
計画書に書く数字には、きちんと“理由”が必要です。
回避法:
- 単価 × 想定客数 × 営業日数 で売上を試算
- 固定費・変動費は事前に見積もりを取る
- 営業時間・対応人数から逆算して妥当性を考える
特に、個人事業主・1人型店舗の場合は、
自分の時間と労力の限界も踏まえた設計が必要です。
③ 想いばかりが強く、行動計画が弱い
例:「夢だったから」「やりたい気持ちが強いです」
想いは大切です。でも、融資審査では“実行力”が見られています。
回避法:
- どんな手順で開業準備を進めるか
- いつまでに何を用意するか
- どんなツール(LINE・SNS・チラシ)で集客するか
など、開業までの「行動スケジュール」も簡単にでもよいので盛り込みましょう。
そもそも創業計画書は「書類」じゃなく「経営の土台」
創業計画書は、
融資を通すための“提出物”ではなく、創業後に迷わず動くための“設計図”です。
一度、しっかりと考えて書いておくことで:
- ブレない方向性が定まる
- 集客や価格設計の軸ができる
- 開業後の行動がスムーズになる
といった“後から効いてくる効果”が大きくなります。
まとめ|「とりあえず書く」のではなく、「未来をつくる」つもりで書こう
創業計画書は、ただ埋めればいいものではありません。
- 誰に届けるか?
- どうやって運営していくか?
- どのくらいの売上を、どうやって得るか?
これらを自分の言葉で言語化することが、経営のスタートラインです。
\無料で相談できます!/
「計画書を書いたけどこれでいいのか不安…」という方は、
LINE登録からお気軽にご相談ください。
あなたの想いと現実をつなぐ“使える創業計画書”を一緒に整えていきましょう!